
「家紋の歴史」について紹介してきた本コラムですが、その第3回で最後になる今回は、「江戸時代以降の家紋の歴史」について解説していきます。江戸時代は、家紋文化がもっとも隆盛を極めた時代だといわれていますが、その歴史や流れについて見ていきましょう。
<「葵紋を禁ずる」とした徳川家の考え方について>
江戸幕府を開いたのが徳川家康であることは、だれもが知っていることです。そしてこの徳川家康は、天下をその手に収めたときに、天皇から菊桐紋を授けられることになりました。これは昔から高貴で尊い家紋であるとされていて、皇室の文様として尊ばれてきました。
しかし徳川家康は、この菊桐紋の下賜を断ります。そして当時広く使われていた「愛紋」を自らの家紋としました。「天皇から下賜された(下賜されそうになった)菊桐紋を断り、家紋を選んだこと」で、葵紋の価値を高めようとしたと考えられています。
ちなみにこののちに、葵紋は徳川家のみの家紋とされ、ほかの人たちはその使用を禁じられることになりました。なおこの「徳川家以外は葵紋を使用してはならない」という決まりができたのは、実は江戸幕府が成立してから100年以降も後のことです。それまで徳川家は比較的家紋の使用については寛大な立場をとっていました。しかし、徳川家と同じ葵紋をつけたものを町人が勝手に売りさばいていたり、この家紋をつけた状態で悪行を働く武士崩れが出てきたりしたことから、徳川家はこれの使用を禁じたともされています。
現在でも根強い人気を誇る「水戸黄門漫遊記」はそのほとんどが創作だとされていますが、その決め台詞に「葵の紋」が使われているのは、「徳川家しか葵紋の使用が許されていなかった=権威と権力を持つ人物である」という分かりやすさから来ているものだと思われます。
ただ、徳川家が葵紋を独占した後も、葵紋の使用を許された家が少ないながらもありました。そのうちのひとつが、「本多家」です。
第1回のコラムでも取り上げましたが、本多家は、徳川家にとって随一の家臣の家系のうちのひとつです。「徳川家の葵紋はもともと本多家を参考にしていたから」などの説もありますが、それでも、徳川家が本多家を特別視していたことを示すエピソードではあります。
このようにして特別に扱われていた葵紋は、やがて皇室の家紋よりもなお高い権威を持つものとして周知されていくようになります。

<大名行列における家紋の役割~武家にとっての家紋の意味とは>
天下泰平の世の中になった江戸時代ですが、この江戸時代においては、「参勤交代」という制度がとられていました。これは、大名家の妻子を江戸に留めおき、地方の大名を1年ごとに領土と江戸に行き来させるという制度です。この参勤交代は、大名の経済力をそぐことおよび妻子を人質として扱うことで、これによって大名の反乱を防ぐことを目的としていました。
このような制度をとっていたため、江戸時代には江戸にやってくる大名たちが「大名行列」を行うことになります。
この大名行列の場面において、家紋は非常に重要な役目を果たしました。大名家にも格付けがあり、格下の大名家は格上の大名家に対して相応の敬意を払わなければなりません。そのたため、家の格を示す「家紋」とその見極めは、非常に重要でした。なおこれをしっかり見定めるために、大名行列の先頭には常に家紋に詳しい人間が置かれたといわれています。
また、大手門には、「その家紋はだれのものか」を判別するための役割を果たす役人が置かれていたと伝えられています。
これは庶民にとっても同じだったようで、すでにこのころには家紋についてまとめた書物も販売されています。ちなみにこの書物は、明治時代までずっと発行され続けていました。なお、識字率が100パーセントではなかったこの時代に、家紋は「文字が読めない人間でも、相手の格を判別できる」という意味で非常に便利なものでもありました。
家紋の歴史は、平安時代に端を発します。より流麗により優雅にと発展していった貴族の家紋と、より簡素により分かりやすくと発展していった武家の家紋は、その性質が大きく異なります。
しかし平安時代に家紋が発展した理由のひとつとして、「牛車が行きかうときなどに、相手の家の格が分かるように」というものがありました。江戸時代における武家の家紋も同じような意味を持っていたことをあわせて考えれば、ここにいたって、貴族の家紋と武家の家紋にも共通点が生まれたといえるでしょう。
<町民文化が花開いた時代、家紋は庶民にも浸透していく>
江戸時代は、町民文化が花開いた時代だとされています。もちろん身分制度は厳格でしたし、将軍家の家紋や大名家の家紋に対する扱いは非常に慎重なものでしたし、こんにちではだれもが持つ「苗字」を名乗ることも一般庶民には許されていませんでした。
しかし「家紋」については例外であり、「将軍家や大名家の家紋を用いないのであれば、厳しい規制はしない」というスタイルを幕府は打ち出していました。
そのため、町民も自分たちを表す家紋を作り出すようになりました。当時は「紋上絵師(もんうわえし)」と呼ばれる家紋のデザインを考える専門家までいました。
・屋号としての「家紋」
現在でも考え方として残る「屋号」ですが、江戸時代にはこの屋号を「家紋」というかたちでのれんなどに染め抜いていました。
江戸時代の日本は世界的に見ても識字率が高かったといわれていて、全国平均で60パーセント以上、江戸の町に限れば70パーセントを超えていたとされています。ただそれでも、江戸時代に生きた人のすべてが文字を読めたわけではないことはすでに述べた通りです。そのため、マークで「どこのお店か」を識別できる家紋の存在は、非常に大きいものでした。
ちなみにこの「屋号としての家紋」の文化は、現在にも息づいています。江戸時代から続くブランド(住友グループ)などは、このときに使われていた家紋をそのまま現在のロゴマークにしています。
・職人の技量を示す「家紋」
士農工商の「工」の職に就く人は、鍛え上げた自分の腕をもって世を渡っていくことになりました。そのため彼らは、自分の仕事であることを示す印を作り出したものに配しました。たとえば武家が使う刀には、刀鍛冶の紋が打たれています。
このような「印」は、やがてその家をも表すものに変わっていきました。職人にとっての家紋とは、自らの家・自らの仕事を示すものであると同時に、自分たちの技量を誇るためのものでもあったのです。
江戸時代における「家紋」の重要性は、主に「商」「工」から語られます。しかし、実質的な意味は持ち得なくても、「農」にもこの家紋を持つ家があったといわれています。
このようにして発展していった家紋文化は、江戸時代が終わり、明治時代以降になっても脈々と受け継がれていきます。現在では家紋を意識するご家庭はそれほど多くはないかもしれませんが、「喪服」の文化にそれが受け継がれています。ちなみにかつては、「女性がお嫁に行くときは、実家で仕立ててもらったことが分かるように嫁ぐ前の家紋を入れた喪服を嫁入り道具として持たせてもらい、嫁いだ後に作る喪服には婚家の家紋を入れた喪服を作る」とする考え方が一般的でした。
お盆が近くなってきたこの時期、家紋を通して改めてご先祖様や家のルーツのことを考えてみてはいかがでしょうか。
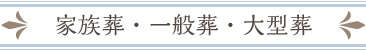
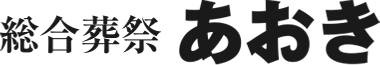












 0120-75-4949
0120-75-4949